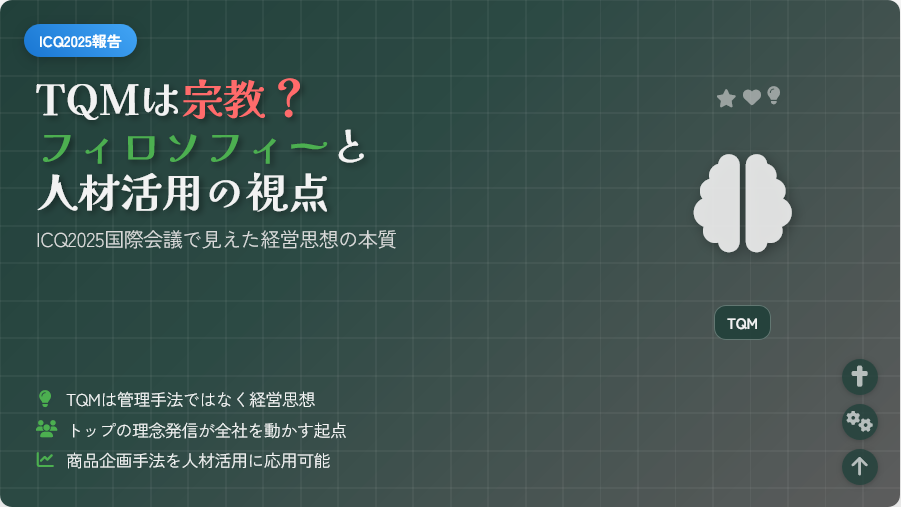9月1日〜4日に東京・新宿で開催された ICQ2025(International Conference on Quality 2025) に参加し、私は「Customer Value Creation and Product Planning Methods in Business Management」というテーマで口頭発表を行いました。
前回のブログでは私自身の発表内容についてご紹介しましたが、今回は会議全体を通じて印象に残った議論、特に 「人材活用」「経営哲学(フィロソフィー)」「TQMの新しい解釈」 についてまとめます。
「TQMは宗教」とまで言われた背景
海外からの登壇者の中には、TQM(Total Quality Management)のことを 「宗教に近いものだ」 と評した方もいました。
一見すると強い表現ですが、ここには深い意味があります。
TQMは単なる品質管理の仕組みではなく、
トップが掲げる 経営哲学(フィロソフィー) を
組織全体に浸透させ、
従業員一人ひとりの行動にまで落とし込む、
まさに「全員参加の思想と文化」として機能しているのです。
トップに求められるのは「数字」ではなく「理念の発信」
特に印象的だった報告は、経営目標や中期計画における トップの役割 についてです。
トップは単に売上や利益といった数字を掲げるのではなく、
「なぜその目標を追求するのか」「私たちは何を大切にしているのか」
という フィロソフィーを語ることが不可欠 だというのです。
さらに、そのフィロソフィーを各部門、そして一人ひとりの従業員が自らの目標や行動に結びつけていくこと。
ここまで落とし込めて初めて、戦略と実行がつながり、TQMの実効性が生まれると報告されていました。
商品企画のデータ思考を「人材活用」へ
私はこれまで、商品企画におけるデータ思考、すなわち顧客の潜在ニーズを発掘し、価値検証を行い、開発コンセプトへとつなげるプロセスに取り組んできました。
今回の議論を受けて強く感じたのは、この手法は 人材活用や人材育成にも応用できる ということです。
例えば:
・顧客観察 → 従業員の体験・行動観察
・潜在ニーズ発掘 → 潜在モチベーションや強みの発掘
・価値検証 → 組織文化や施策の効果検証
このように置き換えれば、商品企画で培った「データに基づく価値創造」は、人材開発の現場でも十分に役立つ可能性があります。
まとめ:理念とデータの橋渡し
ICQ2025全体を通じて、改めて次のことを学びました。
TQMは管理手法ではなく経営思想であること
トップが語るフィロソフィーが全社を動かす起点になること
その理念をデータで補強し、個々の行動に結びつける仕組みが必要であること
私自身は「顧客起点の商品企画」をテーマに研究・実践を続けてきましたが、今後はそれを 「人材起点のデータ活用」 へと広げることで、企業価値の持続的成長に寄与できるのではないかと考えています。
次回の報告では、この「人材活用におけるデータ思考」の具体的な方向性について整理してみたいと思います。